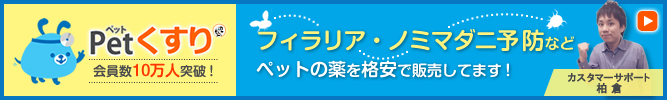だんだんと冬に近づいてきました。寒いのが苦手なのは、人間だけではありません。
猫はもともと中近東などの暑い地方出身であり、そのため寒さが苦手な動物です。
また、最近では寒さが苦手な犬も増えてきました。
今回は、飼い主が寒い時期に気をつけてあげたいことをまとめてみました。
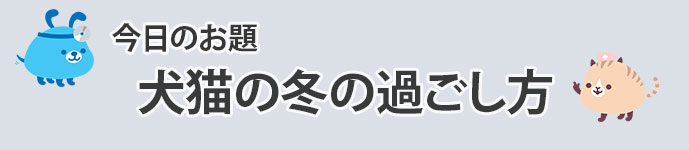
「くしゃみ、鼻水」が出ていたら早めに治そう。
寒くなると空気が乾燥し、人間と同じようにくしゃみや鼻水など呼吸器の症状が出やすくなります。特に猫は猫ウィルス性鼻器官炎(FVR)と総称される人の風邪に良く似た症状の病気に注意が必要です。ワクチン接種で、ある程度防ぐことができる病気ではありますが、猫から猫へ簡単に感染してしまいます。
一度体内に入ってしまったウィルスは、環境によってですが、何年も体にい続けることもあるため、注意が必要です。仔猫や老齢猫は、症状が悪化しやすいため、特に注意が必要です。猫は鼻水により鼻が詰まるとニオイが分からず、食欲不振になり、体力が急激に落ちてしまうので、早めの処理が必要です。クシャミをしていたり、目ヤニや鼻水が出ているようなら、早めの治療を心がけましょう。
気をつけたい暖房器具の使い方と低温やけど。
寒がりのペットでは暖房器具の前に陣取り、体をぎりぎりまで近づける仔もいます。その結果、体毛やひげを燃やしてしまったり、ひどい時には皮膚にやけどを負ってしまうことも少なくありません。ストーブの周りにチャイルドガードなどを設置するなどして、ストーブの本体自体に近づけないようにしましょう。
夜寒いからといって寝床に使い捨てカイロやペットヒーターを設置する方がいますが、それらに長時間、体を密着させることで低温やけどになってしまう場合があります。直接ペットが触れないようにタオルでくるんだり逃げ場をつくってあげて逃げれるように充分気をつけましょう。

水分不足?「おしっこ」の量をチェック!
寒くなるにつれて水を飲む回数や量が減ると、おしっこの量も減り、おしっこは濃くなってきます。また、寒い場所へ行きたがらないのでトイレを我慢してしまうことになり、濃いおしっこが膀胱の中に溜まっている状態になります。このような濃いおしっこは膀胱炎や尿道結石の原因になります。特に、オス猫で去勢している場合は、結石が尿道に詰まって、おしっこが出なくなって下部尿路疾患にかかってしまうことも。
犬猫のおしっこの量が少なくなっていないかチェックしましょう。もし少なくなっている場合は、飲み水をぬるま湯にして、飲みやすくするなど水分を補うことが必要です。トイレの場所も暖かくしてあげるなどしておしっこを我慢することがないようにしてあげましょう。
犬猫が健康に冬を過ごせるように、飼い主も工夫したり、気を配ってあげたいですね。
また、風邪や膀胱炎の症状が重症化する前に治療してあげましょう。
猫風邪の治療薬
アクティバ(ゾビラックスジェネリック)400mg(50錠) |
アクティバ(ゾビラックスジェネリック)800mg(50錠) |
 |
 |
|
猫風邪と呼ばれる猫ヘルペスウイルス感染症、 |
猫風邪と呼ばれる猫ヘルペスウイルス感染症、 猫ウイルス性鼻気管炎の治療薬 アシクロビルという成分はウィルスの少ない初期の発症時に服用するとより効果的です。 |
犬猫の膀胱炎の治療薬
|
|
パセドシンジェネリックノバモックス |
 |
 |
|
膀胱、消火器、気道、生殖器、外耳道の感染症、 |
傷、皮膚の感染、歯の化膿、膀胱の感染、 など幅広く使える治療薬 日本では、サワシリンやバセトシンと言われる、ペニシリン系の抗生物質です。 |
画像引用
www.flickr.com/photos/eiriknewth/1488155293/
www.flickr.com/photos/grumpychris/304968069/