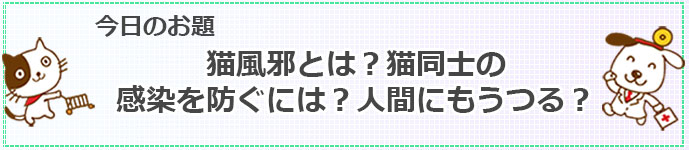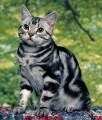こんにちは、オクスリラボです!
今回は、猫風邪とは何かやその原因・症状から始まり、猫風邪の多い季節はあるのか!?予防方法や治療方法について等、色々な猫風邪に関する疑問質問にお答えします!
周りにくしゃみや鼻水の症状がある猫ちゃんはいませんか?猫風邪かもしれません!
まず、そもそも猫風邪とはどんな病気なのでしょうか?
一般的に言われる「猫風邪」とは、猫鼻気管炎ウイルスや猫カリシウイルスの感染によって引き起こされる鼻炎や結膜炎、あるいは喉頭や気管など呼吸器官の炎症を引き起こす病気のことを指します。また、主に結膜炎を引き起こす猫クラミジア感染症も猫風邪と似た症状を示すことから、猫風邪の一つとするケースもあります。
猫風邪は、猫の病気の中でもよく見られる病気です。しかし、治療が遅れると、感染が他の猫にも蔓延したり、症状が重症化して命に関わる状態になったり後遺症が残ることもある非常に厄介な病気です。
猫鼻気管炎ウイルスやカリシウイルス、猫クラミジアが人間にうつることはありません。
しかし、猫同士の感染力はかなり強力で、特に多頭飼育の場合は、接触を断つ対策などを行っても、実際に集団で感染を制御することは非常に難しいことがほとんどです。
猫鼻気管炎ウイルス感染症は、猫ヘルペスウイルスと呼ばれるウイルスによる感染症で、主に発熱や鼻炎(鼻水やくしゃみ)、あるいは目やにを伴った結膜炎が見られます。発熱があると、元気、食欲がなくなってしまい、さらに状態が悪化してしまいます。また、結膜炎は重症化すると目の角膜に潰瘍ができてしまい、場合によっては失明のリスクがありますので注意が必要です。さらにウイルス感染による症状が慢性化した場合には、副鼻腔炎と言って、慢性の鼻づまりや鼻水の症状が続くようになります。これら鼻炎の症状は、猫の嗅覚を失わせてしまうことがあり、食べ物の匂いがかげず、食欲がなくなってしまうこともあります。
猫カリシウイルス感染症では、猫鼻気管炎ウイルスの症状に加えて、さらに口内炎や鼻の周りの皮膚の潰瘍(ただれ)なども見られます。特に口内炎が生じると、痛みから食べ物を食べることができなくなり、痩せてしまったり、栄養状態が悪化し、さらに症状が重篤になることがあります。このような場合、ごはんに見向きもしなくなるというよりは、ごはんの前で食べたそうにするけど、食べられないような仕草を見せます。一般的には、猫鼻気管炎ウイルス感染症と猫カリシウイルス感染症の症状は似通っているのですが、猫カリシウイルス感染症の方がより重症になることが多いです。
また、猫クラミジア感染症では、重度の結膜炎(目のまぶたのが腫れ上がる症状)が認められます。結膜炎や気管支炎なども認められますが、一般的には猫鼻気管炎ウイルス感染症やカリシウイルス感染症の症状よりは軽いことが多いです。
さらにいずれの感染症も、重症化すると、元気消失、食欲不振などの全身状態の悪化も見られるようになります。中には、感染により免疫力が低下してしまうと、一つだけのウイルス感染ではなく、複数のウイルスや細菌が感染してしまうことがあり、その場合にはより重症化してしまいます。
これらの感染症は持続感染、つまり臨床症状は改善してもウイルスを体内に持ち続けている状態となるため、季節に関係なく猫同士の接触によって感染します。そのため外に出る猫は季節を問わず感染しますし、特に多頭飼育環境では、衛生環境を徹底的に改善しなければ、ウイルスが蔓延してしまいます。
つまり、人間の風邪と異なり、季節的な要因よりも、病原体を保持している外猫との接触や多頭飼育という環境的な要因がより重要になります。
ほとんどがウイルスを持っている猫と接触することで感染します。直接的な接触だけでなく、感染して発症している猫の目やにや鼻水が感染源になることがありますので、同じ容器でお水を飲んでいたり、あるいは感染している猫の食器を舐めてしまうなどの行為により感染してしまうこともあります。
また、母子感染も見られ、母親がウイルスを持っている場合、子猫が4〜5週齢に達したあたりから、症状が見られるようになります。
ウイルスによる猫風邪の治療は、ウイルスに対する特効薬がないため、対症療法が中心となります。
目やにや鼻汁の症状だけで、食欲が落ちていない間は、インターフェロン療法や二次感染予防(ウイルスで体が弱まると細菌感染も起こしやすくなり、より重症化する恐れがあります)のための抗生物質の内服、点眼を行います。また、食欲が落ちている場合は、輸液療法も実施します。これらは即効性があるものではなく、あくまでウイルスと戦う猫の体を支えるための治療ですので、状態が改善するまでに数日から数週間という時間がかかります。
特に鼻汁などの鼻炎症状があると、嗅覚が低下してしまうのですが、猫は嗅覚が低下するとごはんの匂いがかげず、結果として、食欲が刺激されないため、全くごはんを食べなくなることがあります。厄介なことに、猫は24時間以上、ごはんを食べない絶食状態が続くと、肝リピドーシスという肝臓の病気を発症することもあるため、食欲がない場合は速やかに動物病院を受診するようにしてください。重度の食欲不振の場合は、食道チューブや胃チューブなどを用いてでも食事をとっていく必要があります。
状態がそこまで悪化しておらず、自宅で様子をみる場合は、ウェットフードを温めて、匂いがしっかり出るようにしてあげることで食べられることもあります。
猫カリシウイルス感染症での口内炎による食欲の低下も、全く食べない時は、上記のような食道チューブや胃チューブの設置が必要になることもあります。ただ、中にはドライフードのような硬い食事を、ウェットフードのような柔らかい食事に変更したりすることで食べることもあります。
また、動物病院を受診する際は、ウイルス性の猫風邪は伝染力の強い感染症ですので、待合室で他の猫と接触させないようにしましょう。入院治療が必要な場合でも、隔離室での入院や消毒の徹底など、特殊な対応が必要となり、動物病院によっては猫風邪の入院治療ができないところもあります。かかりつけであっても、必ず受診前に電話などで事前に相談するようにしましょう。
クラミジア感染症に対しては、テトラサイクリン系と呼ばれる抗生物質が有効で、他に感染している猫との接触を避けるなどの環境整備ができていれば、比較的速やかに治療することができます。
また、いずれの感染症も治療期間中は、他に原因ウイルスやクラミジアを持っている猫との接触を避け、飼育環境の消毒を徹底します。

まずはこれらのウイルスやクラミジアを保有する猫と接触しないようにすることが重要です。
外に出る猫は、完全室内飼育にします。また、多頭飼育の場合は、これら感染症を発症した猫を完全に隔離します。つまり部屋を完全に分けるようにします。中には、同じ空間で、間仕切りやケージなどを利用して隔離するケースがあるのですが、これらの感染症は、目やにや鼻水を介して感染することも多く、同じ空間ではそれらの感染を防ぐことは非常に困難です。必ず部屋を分ける、飲み水や食べ物の食器を分けるなど、空間的に完全隔離できるようにします。
さらに、これらの食器など猫が触れるものは、使用後必ず消毒してください。また人間も感染している猫に接触する前後で、使い捨て手袋やエプロンを着用し、できる限り感染猫に直接触れないようにしましょう。
また、これら猫風邪に対する予防接種も有効です。外に出る猫、多頭飼育の猫は必ず接種してあげてください。また、完全室内飼育の猫でも、アクシデントで外に出てしまったり、あるいは外の猫が家の近くに来て、接触してしまうリスクもありますし、動物病院を受診したり、ペットホテルなどを利用することもありますので、なるべく接種することをお勧めします。しかし、これらの予防接種は、感染を防ぐものではなく、感染後の症状の発症を最小限に止めるものです。
また、猫の中には予防接種によって体調を崩してしまう猫もいますので、接種にあたっては必ず獣医師の診察を受け、ワクチンの種類などを相談した上で受けるようにしてください。
さらには、猫自身の免疫力を高く保っておくことも重要です。特に多頭飼育の場合は、同居猫同士のストレスから、免疫力が低下している猫が多くいます。その場合はやはり病気をもらいやすくなりますので、それぞれのテリトリーを確保してあげたり、トイレやお水の場所を複数箇所(理想は飼育頭数プラス1)準備してあげるなど、できるだけストレスを軽減する環境を準備してあげてください。
一度かかってしまうと厄介な猫風邪。このブログの内容が予防やできるだけ早い病気の発見につながれば幸いです!
【その他の記事】
▼ペットくすりでは、猫風邪のお薬も取り扱っております。▼
| ゾビラックス200mg25錠 | ゾビラックスジェネリック400mg50錠 |
 |
 |
|
猫風邪と呼ばれる猫ヘルペス |
ゾビラックスのジェネリック! |
参照画像:http://www.flickr.com/photos/30054343@N07/29404514265、http://www.flickr.com/photos/98413464@N03/26637853142